 新・端数期間暦年計算書
過払金利息利率も
新・端数期間暦年計算書
過払金利息利率も変動利率入力自由自在!!
改正民法変動利率に、完全対応!!
トピックス
◯バージョンV20230903で 「特別要望提供版」として「裁判所書記官用過払金利率変動入力可能2000行版」を追加しました。
◯バージョンV20230903で 「特別要望提供版」として「裁判所書記官用過払金利率変動入力可能2000行版」を追加しました。
端数期間暦年計算とは
裁判所が採用している計算方式です。年は年単位で計算したうえ、1年に満たない端数の期間については平年と閏年とで別個に利息金計算をしたうえで合計する計算方式です。
裁判所が採用している計算方式です。年は年単位で計算したうえ、1年に満たない端数の期間については平年と閏年とで別個に利息金計算をしたうえで合計する計算方式です。
2020年から改正民法変動利率制が施行されます。
これにともない、裁判所が採用している端数期間暦年での利息計算でも変動利率での利息計算が必須になります。
株式会社頭脳集団制作の「新・端数期間暦年計算書」は、すでに変動利率計算に対応しており、利率を自由自在に指定することができます。いままで多くの訴訟実務でも利用実績がある信頼できる金利計算プログラムです。
利息金計算といっても、年利計算と非年利計算があります。また、年利計算には二種類の計算構造と多様な計算方法があります。
「新・端数期間暦年計算書」には次の6種類の計算書を収録しています。実務用途に合わせてご利用ください。
新・端数期間暦年計算書
(V20230903)
定価 : 11330円(税込み)
送料無料
USBメモリで提供
制作: 株式会社頭脳集団
販売: 有限会社オブアワーズ
稼働前提条件:
◯ マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。
◯ ご提供する計算書は、EXCEL97-2003形式のエクセルシートです。これが動作するEXCELでご利用ください。
(V20230903)
定価 : 11330円(税込み)
送料無料
USBメモリで提供
制作: 株式会社頭脳集団
販売: 有限会社オブアワーズ
稼働前提条件:
◯ マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。
◯ ご提供する計算書は、EXCEL97-2003形式のエクセルシートです。これが動作するEXCELでご利用ください。
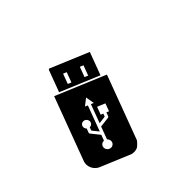
USBメモリで提供
計算の目的と計算書 1
- 破産債権、更正債権など諸債権金額届け出計算
- 差押え、仮差押え手続きにおける債権金額計算(端数処理東京地裁方式、大阪地裁方式選択可能)
- 差押え、仮差押え手続きにおける債権金額計算
- 強制執行手続きにおける請求債権金額計算
- 訴状に記載する請求債権金額計算
- (単発)元利金金額計算
- (単発)利息金額計算(内金利息金計算含む)
- (単発)遅延損害金額計算
- その他
- (端数処理東京地裁方式、大阪地裁方式選択可能)
端数の切り捨て処理の時期が大阪と東京では異なっています - (内金利息金計算可能)
元金の一部についてのみ利息金を発生させる場合 - (利息制限法利率計算可能)
法律で利息金利率の上限は決められています - (西暦換算機能付き)
- (年、端数期間平年閏年別利息金額表示)
年、平年閏年別の端数日数を表示します
計算の目的と計算書 2
(反復弁済追加借入)利息金額計算
計算行数が多くなるとファイルの容量が大きくなります
- (反復弁済追加借入)元利金金額計算
- (反復弁済追加借入)利息金額計算
(反復弁済追加借入)利息金額計算
計算行数が多くなるとファイルの容量が大きくなります
- (年、平年閏年別端数期間日数表示)
年、平年閏年別の端数日数を表示します - (過払金、過払金利息、累計利息金表示選択可能)
過払金や過払金利息の計算もできます - (計算書引継機能付き)
計算書の計算結果を新しい計算書に引き 継ぐことができます - (入力ミス指摘警告表示機能付き)
入力ミスがなされた場合、警告表示がでます
計算の目的と計算書 3
- 判決などにみられる元金内金利息金計算
- 内金に利息計算する反復弁済計算書です
計算の目的と計算書 4
- 複利利率による元利金計算
- 好きなところから利息金を元金に入れることが可能です
計算の目的と計算書 5
- 利息金前払い場合の利息制限法2条計算
- 利息の前払いをさせられたときの利息制限法計算です
計算の目的と計算書 6
- 利息金前払い場合の利息制限法2条計算
- 追加借入をした場合の追加借入当日を含む日数表示計算書です