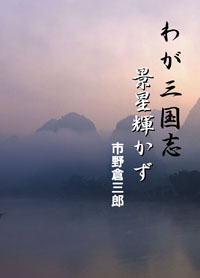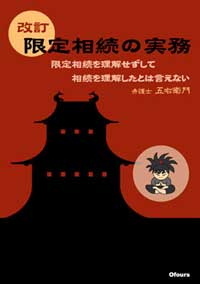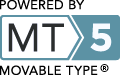- 更新日:
- 改訂限定相続の実務
(著者からの言葉?弁護士五右衛門・大阪弁護士会服部廣志より)
法律と税務が交錯する「限定相続」については、弁護士も会計士、税理士も、その不勉強が理由で避けてきた。
「限定相続は危険だから避けた方がいい」と言う人もいる。マクロ的には限定相続をした者を保護するための「みなし譲渡所得課税の制度」がミクロ的には限定相続人に不利益を与えるという側面もあること、そして、限定相続の特質ともいうべき「責任限定の制度」等を正しく理解しないことに起因すると思われる。
専門家がこの限定相続から逃避し避けることにより、多くの限定相続を相当とする相続事件が単純相続ないし相続放棄という形態を選択させられることとなり、法律が予定した限定相続の採用が見送られてきた。
限定相続についての法律規制と税務を正しく理解し、その選択を誤ることがなければ、この制度が多種多様な相続事案に活用できる優れた制度であることがわかる。
- 更新日:
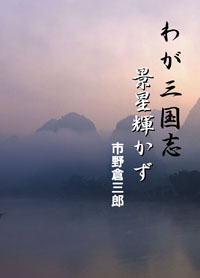
市野倉三郎 著
ISBN978-4-902182-13-2
A5判2段組520頁
発行 オブアワーズ
定価 2520円(本体2400円+税)
幼い頃から私は中国の物語りに魅せられ、とりわけ三国志演義は水滸伝、西遊記と共にくり返し読みふけりましたが、そのうちに演義の内容にどうも納得がいかなくなりました。余りにも蜀の人物を持ち上げ、魏、呉の人物をおとしめていますし、かなり荒唐無稽な話も目に付きます。やがて陳寿の正史を読むに及んで人物像にかなりの隔たりがあり、三国時代は孔明の死で終わったわけではない事も知りました。
そこで自分なりの解釈を試み、実像に迫りたいと思い立ち、いくつかの作品を同人誌「浮標」に載せ、かなりの量になった所で改めて手を加え、一冊にまとめたものが本書であります。
(あとがき から)
- 更新日:
- 改訂限定相続の実務
そもそも、「限定相続」という用語は、法律では使われていません。五右衛門さんが、7年前に「限定相続の実務」を執筆されるときに、法律で定めるところの「限定承認をして相続すること」を、ひと言で「限定相続」と表現したのが切っ掛けです。いわば、五右衛門さんの造語なのです。
一方、相続に際して、限定承認を使っての方法を解説した実務書は、「限定相続の実務」しか発行されていませんでした。このため、多くのみなさんに、ご購読、ご利用いただきました。そして、最近では、限定承認して相続することを、「限定相続」と言われるようになってきました。
ちょっとした豆知識のご紹介でした。